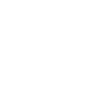資格・免許案内
児童学科で取得可能な資格・免許について
児童学科では、子どもに関わる多様な専門職への道をひらく、さまざまな資格・免許の取得が可能です。
子どもと家庭、そして社会をつなぐ幅広いフィールドで活躍するために、体系的なカリキュラムと実践的な学びを通して専門性を高めていきます。
具体的には、所定の科目を履修することで、教員免許(幼稚園/中学校・高等学校[家庭])や保育士資格に加え、絵本に関する専門的な知識と実践力を身につける「認定絵本士」など、進路や関心に応じた資格の取得が可能です。
また、卒業後に活かせる任用資格として、児童福祉司、児童指導員、社会福祉主事なども取得できます。
幼稚園教諭一種免許状
子ども理解に優れた幼稚園教諭を社会に輩出することを目指し、取得可能なカリキュラムを構成しています。
免許取得のためには、2年次の秋に教職課程履修の申し込み・面接を経て、3年次4月から正式に履修が始まります。
教育実習は、3年次の秋と4年次の春に2回実施され、実習先は関東近県の私立幼稚園や東京都内の公立幼稚園などから、児童学科が依頼・決定します。
中学校・高等学校(家庭)一種免許状
中学校および高等学校の家庭科教員免許が取得できます。こちらも、2年次の秋に教職課程履修の申し込み・面接を経て、3年次4月から正式に履修が始まります。
教育実習は4年次春に3週間実施され、実習先は本人の出身中学校または高等学校に依頼することが多く、依頼が難しい場合には大学が実習先を確保します。
家庭科では「保育」分野も扱われますが、児童学科出身の家庭科教員は、家政学の中でも特に「保育」の専門性を備えた人材として、子どもの成長・発達、家族や家庭のあり方を幅広く学び、児童学・保育学の知見を活かして活躍することが期待されます。
保育士
保育者養成コースに所属し、所定の単位を修得することで、卒業と同時に保育士資格を取得できます。
コースへの登録は、1年次秋の面接を経て、2年次から正式登録となります。所属人数には上限がありますが、保育士資格は国家試験によって取得することも可能です。
本コース所属者は、2週間×3回の保育実習を行います。また、原則として「幼稚園教諭一種免許状」もあわせて取得します。
認定絵本士
3年次までに指定された科目を履修することで、在学中に「認定絵本士」の称号を得ることができます。養成人数には制限があり、希望者が多数の場合は、1年次に選考を行います。
「認定絵本士」とは、絵本や出版、子どもの読書活動に関する専門的な知識、絵本を用いた多様な活動に必要な技能、そして絵本の魅力を深く理解する感性を身につけた者に対して、絵本専門士委員会(国立青少年教育振興機構)が認定する資格です。
資格取得後は、地域や職場において絵本の魅力や可能性を伝える役割が期待され、読書活動の推進にも貢献できます。さらに、こうした活動を通じて実務・実践経験を積み、資質と能力がふさわしいと委員会に認められた場合には、絵本の専門家として「絵本専門士」に認定される道も開かれています。
任用資格として取得できるもの
児童福祉司
卒業後、都道府県の公務員として採用され、厚生労働省指定の児童相談所や児童養護施設などで1年以上の相談援助業務に従事することで、任用資格が得られます。
児童指導員
卒業後、公務員(都道府県・市町村)または民間の児童福祉施設に採用された際に任用される資格です。
社会福祉主事
地方自治体の福祉事務所などで、福祉サービスを必要とする人に生活指導や相談、各種手続きを行うための任用資格です。
大学在学中に「社会福祉主事に関する指定科目」を修得し、卒業することで資格が認められます。